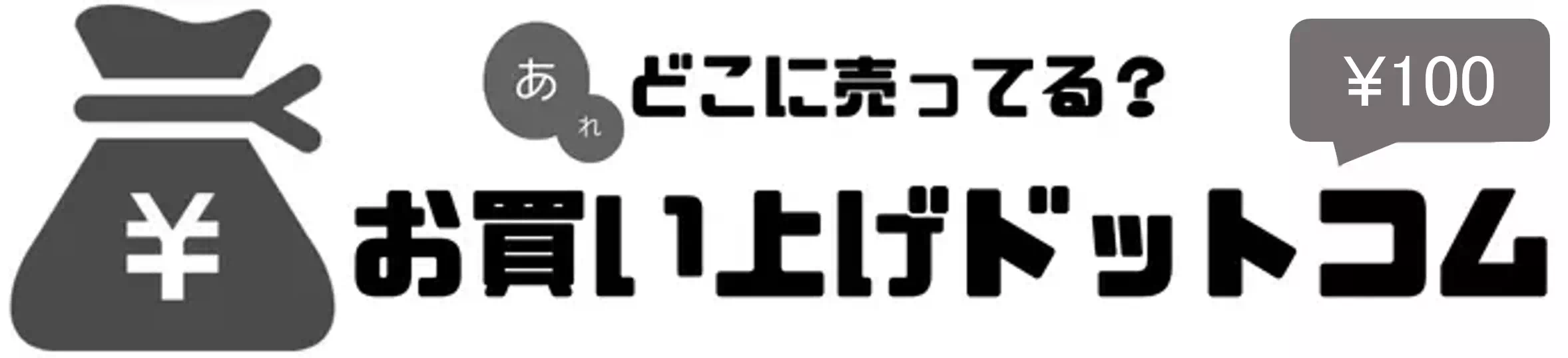100均で見かける延長コード、その安さと手軽さから、つい手に取ってしまいますよね?でも、その電源タップが本当に安全なのか、考えたことはありますか。
「安いから大丈夫かな」という小さな不安は、実は火事や火災といった大きな事故への警告かもしれません。
特に便利な4個口タイプや、部屋の隅々まで届く5mの延長コードは、知らず知らずのうちに許容電力を超えてしまう危険な落とし穴が潜んでいます。
事実、過去には大手100均のダイソーで、製品の自主回収が行われた事例もあるのです。
だからといって、100均の製品がすべて危険というわけではありません。
大切なのは、製品ごとの違いを正しく理解し、安全に使うための知識を持つことです。
この記事では、100均の延長コードが本当に大丈夫なのか、その安全性を徹底的に深掘りします。
ダイソー、セリア、キャンドゥといった店舗ごとの特徴や、家電量販店の電源タップとの明確な違い、そして火事を防ぐための具体的な選び方まで、あなたのすべての疑問に答えます。
この記事を最後まで読めば、もう延長コード選びで迷うことはありません。
正しい知識を身につけ、火災のリスクからあなた自身と大切な家族を守りましょう。
記事の要約とポイント
- 【結論】100均延長コードは大丈夫?火事・火災のリスクと安全に使える条件を解説
- 【危険性】便利な4個口や5m電源タップの落とし穴!許容ワット数を超えた時の違いとは?
- 【店舗比較】ダイソー・セリア・キャンドゥ!各社の延長コードの特徴と注意点まとめ
- 【選び方】過去の回収事例から学ぶ!火事を起こさない安全な100均電源タップの見分け方
「たった100円で延長コードが買えるなんて、なんて便利な時代なんだろう」。
近所の100均ショップで、カラフルなパッケージの電源タップを手に取ったあなたは、そう思ったかもしれません。
でも、その心の片隅で、小さな声が聞こえませんか?
「こんなに安くて、本当に大丈夫なのだろうか…」と。
ええ、その感覚はとても正しい。
何を隠そう、この道30年以上の私も、若かりし頃にその「安さ」に釣られて、ヒヤリとした経験があるのです。
ある冬の寒い夜、ジジ…という不気味な音と、プラスチックが焼けるような異臭で目が覚めたことがありました。
慌てて音のする方へ向かうと、安物の延長コードのプラグ部分から、か細い煙が立ち上っていたのです。
結論から申し上げましょう。
100均の延長コードは、条件付きで大丈夫です。
しかし、その「条件」を知らずに使うことは、時限爆弾のスイッチを押しながら生活するようなもの。
この記事では、家電量販店で売られている数千円の製品と、ダイソーやセリア、キャンドゥに並ぶ製品との間にある、目には見えない決定的な違い、そして火事という最悪の事態を避けるための知恵を、私の経験を交えながら余すことなくお伝えしていきます。
さて、まず大前提として理解していただきたいのは、電気製品の安全性における「価格」の意味です。
一般的に、延長コードや電源タップの価格の違いは、主に3つの要素から生まれます。
第一に、内部に使われている導線(銅線)の質と太さ。
第二に、全体を覆う絶縁被覆やコンセント本体のプラスチック樹脂の品質。
そして第三に、過電流保護や雷サージ、ホコリ防止シャッターといった「付加的な安全機能」の有無です。
100均で販売されている製品は、これらの要素を、法律で定められた最低限の安全基準(PSEマークがその証です)をクリアする範囲で、極限までコストカットして作られています。
だからこそ、あの価格が実現できるわけです。
ここで、私の失敗談を一つ。
あれは私がまだ20代前半、電気工事の仕事を始めたばかりの頃でした。
自分の部屋に置いた小さな電気ストーブのコードが短く、壁のコンセントまで届かない。
そこで近所の雑貨店で、当時としては破格の安さだった延長コードを購入したのです。
もちろん、今でいう100均のようなクオリティのものでした。
「ストーブくらいなら大丈夫だろう」と高を括って使い始めた数日後、例の事件が起きました。
幸い、火事になる前に気づいたため大事には至りませんでしたが、延長コードのプラグは熱で溶け、壁のコンセントも黒く焦げ付いていました。
原因は明白。
ストーブの消費電力が、その安物延長コードの許容できる電力を大幅に超えていたのです。
コード自体も触るとほんのり温かくなっており、まさに火災の一歩手前でした。
この経験から私が学んだのは、「大丈夫だろう」という根拠のない自信が最も危険だということ。
そして、製品に記載されている「合計〇〇Wまで」という数字の意味を、本当の意味で理解することの重要性です。
家電量販店の製品との違いは、この許容電力に余裕があるか、ギリギリかという点にも現れます。
安全マージンがたっぷりとられた製品と、最低限の基準で作られた製品。
その違いが、いざという時の結果を大きく左右するのです。
あなたの家のコンセント周りは、今どうなっていますか?
一度、その目で確かめてみてください。
100均延長コードの真実!火事リスクと安全性
100均
延長コード
大丈夫
火事
違い
100均の延長コードが本当に大丈夫か結論から解説。1500Wなどの許容ワット数を守れば安全ですが、使い方を誤ると火事や火災のリスクがあります。家電量販店の電源タップとの決定的な違いや、過去にダイソーで起きた回収事例も紹介。特に危険な4個口や5mコードの落とし穴を知り、安全に使いましょう。
- なぜ危険?100均延長コードで火事・火災が起こる仕組み
- 過去にはダイソーで回収事例も!確認すべき危険な製品とは
- 特に注意!便利な4個口や5mの延長コードに潜む危険性
なぜ危険?100均延長コードで火事・火災が起こる仕組み
前の章で、私の苦い体験をお話ししました。
では、なぜ許容電力を超えたり、品質の低い延長コードを使ったりすると、火事や火災といった深刻な事態に発展してしまうのでしょうか。
その仕組みを理解することは、危険を回避するための第一歩です。
電気は見えないからこそ、その裏側で何が起きているのかを知っておく必要があります。
まず、最も基本的な原因は「ジュールの法則」という物理法則にあります。
難しく聞こえるかもしれませんが、要は「電気の通り道が狭い(抵抗が大きい)場所に、たくさんの電気(電流)を流そうとすると、熱が発生する」というシンプルな原理です。
これを延長コードに当てはめてみましょう。
100均などで安価に販売されている製品の一部は、コストを抑えるために内部の銅線が細く作られていることがあります。
細い銅線は、電気にとって「狭い道」です。
そこに、電気ストーブやドライヤー、電子レンジといった大量の電気を必要とする家電を接続すると、銅線は電気の流れに耐えきれず、まるでマラソンで限界を迎えた選手のように、熱をどんどん発し始めます。
この熱が、コードを覆っているビニールの被覆を溶かし、最悪の場合、プラスとマイナスの線が直接触れ合う「ショート(短絡)」を引き起こします。
ショートが起きると、瞬間的に莫大な電流が流れて火花が散り、周りのホコリや可燃物に着火して火災に至るのです。
実際に、私は仕事柄、発火した電源タップを何度も目にしてきました。
2019年の冬だったと記憶しています。
あるお客様から「コンセントから煙が出た」と緊急の連絡を受け、現場に駆けつけました。
リビングの隅には、黒く焼け焦げた電源タップが転がっており、壁紙の一部もススで汚れていました。
幸い、ご家族がすぐに気づいてブレーカーを落としたため、ボヤで済みましたが、一歩間違えれば家全体が火の海になっていたかもしれません。
その電源タップは、お客様がお子さんのために雑貨店で購入した、キャラクターものの可愛らしい4個口タップでした。
そこには、テレビ、ゲーム機、そして出力の大きい加湿器が接続されていました。
分解してみると、案の定、内部の銅線は許容電流に対してギリギリの細さ。
長期間の使用による劣化と、加湿器という想定外の負荷が重なり、限界を超えてしまったのでしょう。
これが、安価な製品に潜む構造的な危険性なのです。
もう一つ、非常に恐ろしいのが「トラッキング火災」です。
これは、コンセントとプラグの間に溜まったホコリが、湿気を吸うことで電気の通り道(トラック)を作り出し、やがて放電(スパーク)を繰り返して発火する現象を指します。
特に、冷蔵庫やテレビの裏など、普段あまり掃除をしない場所に差しっぱなしのコンセントは要注意です。
品質の高い電源タップは、プラグの刃の根元に「トラッキング防止絶縁カバー」がついていたり、コンセントの差し込み口にホコリの侵入を防ぐ「シャッター」がついていたりと、このトラッキング火災を防ぐための工夫が凝らされています。
しかし、100均の製品では、こうした安全機能が省略されているケースも少なくありません。
ほんの少しの構造の違いが、安全性を大きく左右する。
あなたが今使っている延長コードのプラグの根元、どうなっていますか?
一度、抜いて確認してみることを強くお勧めします。
大丈夫だと思っていても、そこには見えない危険が潜んでいるかもしれないのですから。
過去にはダイソーで回収事例も!確認すべき危険な製品とは
「専門家の話は分かったけれど、100均とはいえ、あのダイソーのような大企業が危険なものを売るはずがないだろう」。
そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。
もちろん、企業は安全基準に基づいて製品を製造・販売しています。
しかし、残念ながら、過去にはその基準をクリアしたはずの製品が、市場に出た後で不具合が見つかり、自主回収(リコール)に至ったケースが実際に存在するのです。
これは、決してダイソーだけを責める話ではありません。
あらゆるメーカーで起こりうることですが、私たち消費者は、そうした事実があったことを知り、自分の身を守るための知識として活かすべきです.
特に記憶に新しいのは、数年前にダイソーが発表した一部の延長コードの回収事例です。
対象となった製品は、特定の期間に販売されたもので、内部の構造に不備があり、使用状況によっては発煙や発火に至る恐れがある、という内容でした。
このニュースが流れた時、私の事務所の電話は鳴りっぱなしでした。
「うちで使っているダイソーのコードは大丈夫か」「どの製品が危ないのか」といった問い合わせが殺到したのです。
あるお宅に伺った際、回収対象となっているまさにその製品が、お子さんの勉強机の足元で使われているのを発見しました。
その時のご両親の血の気が引いたような表情は、今でも忘れられません。
「いつも使っていたのに、まさか…」と。
この一件は、PSEマークが付いていても100%安全とは限らない、という厳しい現実を私たちに突きつけました。
製造過程でのわずかなズレや、設計上の想定漏れが、時として大きな事故に繋がる可能性があるのです。
では、私たちはどのようにして危険な製品を見分け、自分の身を守ればよいのでしょうか。
まず、基本中の基本として、製品本体やパッケージに記載されている情報を必ず確認する癖をつけてください。
確認すべき危険なサインは、以下の通りです。
- 許容電力(W数)が低い、または記載がない:
家庭用のコンセントは、一つの差し込み口で1500Wまで使えるのが基本です。
延長コードも「合計1500Wまで」と記載されているものを選ぶのが大原則。
もし、1200Wや1000Wといった低い数値が書かれている場合、それは使える家電がかなり限定される「低出力用」の製品です。
ましてや、どこにも記載がない製品は、論外と言わざるを得ません。 - コードが不自然に硬い、または細い:
コードを軽く曲げた時に、ゴワゴワと不自然に硬い感触がするものは、内部の銅線が劣化していたり、被覆材の品質が低かったりする可能性があります。
また、見た目にも明らかに他の製品より細いコードは、許容できる電流が低いと考えられます。 - プラグの刃がグラグラする:
プラグ部分を指で軽く揺すってみてください。
刃の根元が少しでもグラつくような製品は、内部の接触不良を起こしやすく非常に危険です。
しっかりと固定されているものを選びましょう。
そして、最も重要なのは、定期的にリコール情報をチェックする習慣です。
消費者庁の「リコール情報サイト」などでは、製品名やメーカー名で回収対象になっていないかを確認できます。
特に、長年使っている延長コードがある場合は、一度調べてみることをお勧めします。
あなたが信頼して使っているその製品が、いつの間にか「危険な製品」リストに載っている可能性も、ゼロではないのですから。
特に注意!便利な4個口や5mの延長コードに潜む危険性
さて、ここまでは延長コードそのものの品質についてお話ししてきました。
しかし、火災の危険は、製品の品質だけでなく、私たちの「使い方」によっても飛躍的に高まります。
特に、多くの人が「便利だから」という理由で何気なく使っている「4個口などの多口電源タップ」と「5mなどの長い延長コード」。
この二つには、思わぬ落とし穴が潜んでいるのです。
まずは、4個口の電源タップについて。
差込口がたくさんあるというのは、一見すると非常に便利です。
テレビ周りやデスク周りなど、コンセントが一つしかない場所で複数の機器を使いたい場合には、まさに救世主のように思えるでしょう。
しかし、ここに最大の罠があります。
差込口が多いと、人はつい、そのすべてを使いたくなってしまうのです。
これが危険な「タコ足配線」の始まりです。
ここで、具体的な数字で考えてみましょう。
壁のコンセント一つから取れる電力の上限は、先ほどからお伝えしている通り、合計1500Wです。
これは、電源タップの差込口がいくつあろうと変わりません。
大元は一つなのです。
仮に、あなたが冬のリビングで、4個口のタップに以下の家電を接続したとします。
- テレビ(約200W)
- こたつ(強運転で約600W)
- スマートフォン充電器(約20W)
この時点での合計は、200 + 600 + 20 = 820W。
まだ余裕がありますね。
しかし、そこへ「空気が乾燥してきたから」と、加湿器(パワフルなもので約700W)を追加したらどうなるでしょう。
合計は、820 + 700 = 1520W。
この瞬間、上限である1500Wを超えてしまいました。
さらに、もし「ちょっとお茶を」と電気ケトル(約1200W)を繋いでしまったら…もうお分かりですね。
合計は2720Wにもなり、これは完全にキャパシティオーバーです。
結果として、延長コードは異常発熱し、ブレーカーが落ちるか、最悪の場合は発火します。
私が駆けつけた火災現場の多くが、この「ちょっとくらいいいだろう」という油断から始まったタコ足配線が原因でした。
4個口という便利さが、かえって危険を呼び込んでしまう典型的な例です。
次に、5mの延長コードのような、長い製品の危険性です。
部屋のレイアウト上、どうしてもコンセントから遠い場所で電気を使いたい時、長いコードは重宝します。
しかし、コードは長くなればなるほど、電気抵抗が大きくなるという性質を持っています。
これにより「電圧降下」という現象が起こり、機器に十分な電力が供給されず、正常に作動しなかったり、コード自体が熱を持ちやすくなったりします。
さらに危険なのが、多くの人が無意識にやってしまう「コードを束ねて使う」行為です。
「5mも必要ないから、余った分はクルクルと巻いておこう」。
この親切心が、実は非常に危険なのです。
コードを束ねると、コード自身が発した熱の逃げ場がなくなり、内部にどんどん熱がこもっていきます。
例えるなら、ダウンジャケットを着て全力疾走しているような状態です。
熱がこもった結果、ビニールの被覆はあっという間に溶け始め、ショートして発火に至ります。
特に、カーペットの下に束ねたコードを隠したり、家具の裏でホコリまみれになったりしている状態は最悪です。
長いコードは、踏みつけられたり、ドアに挟まれたりして、内部の銅線が断線しかかっている(半断線)ことにも気づきにくい。
見た目は何ともなくても、内部では危険な状態が進行しているケースが多々あるのです。
あなたの家の長い延長コード、今、どのような状態で使われていますか?
便利さの裏に隠れた危険性を、今一度、見直してみてください。
【店舗別】この100均延長コードなら大丈夫!安全な選び方
ここまで、100均の延長コードに潜む様々な危険性について、少し怖い話も交えながら解説してきました。
「もう100均で延長コードを買うのはやめよう…」と思われたかもしれません。
しかし、お待ちください。
私の目的は、皆さんを怖がらせることではありません。
正しい知識を持って、製品を正しく選び、安全に使ってもらうこと。
それが専門家としての私の願いです。
100均の製品も、選び方と使い方さえ間違えなければ、私たちの生活を豊かにしてくれる強い味方になるのです。
この章では、いよいよ実践編として、ダイソー、セリア、キャンドゥといった店舗ごとの特徴を踏まえつつ、火事を起こさないための具体的な「安全な選び方」を伝授しましょう。
まず、どの100均ショップで選ぶ場合でも、絶対に守ってほしい共通のチェックリストがあります。
これを頭に入れておくだけで、危険な製品を掴むリスクを大幅に減らすことができます。
【安全な100均延長コード選びの鉄則5か条】
- 「PSEマーク」の有無を必ず確認する:
これは日本の電気用品安全法で定められた、安全の最低基準を満たしている証です。
このマークがない製品は、法律違反の可能性があり、絶対に購入してはいけません。
ひし形のPSEマークと丸形のPSEマークがありますが、延長コードの場合は丸形がほとんどです。 - 「合計1500Wまで」の表示を確認する:
パッケージや製品本体のどこかに、必ず定格容量が記載されています。
「15A 125V」「合計1500Wまで」といった表記を探してください。
この数字が低いものは、使える機器が限られるため、汎用性を考えると1500Wのものを選ぶのが最も安全で間違いありません。 - トラッキング火災防止機能をチェックする:
プラグの刃の根元を見てください。
黒やグレーの樹脂で覆われている「絶縁カバー」が付いている製品を選びましょう。
これが、ホコリによる火災(トラッキング火災)を防ぐための重要な機能です。 - コードの太さと質感を触って確かめる:
可能であれば、パッケージの上からでもコードを触ってみてください。
極端に細いものや、しなやかさがなくゴワゴワと硬いものは避けましょう。
しっかりとした太さと、柔軟性があるものが理想です。 - プラグやコンセント部分の作りを確認する:
プラグの刃がグラグラしていないか、コンセントの差し込み口のプラスチックが安っぽすぎないか、バリなどがないかを目で見て確認します。
細部の作り込みに、その製品の品質が現れます。
さて、この鉄則を踏まえた上で、大手3社の傾向を見ていきましょう。
まず、業界最大手のダイソーです。
ダイソーの強みは、何といってもその圧倒的な品揃え。
シンプルな延長コードだけでなく、個別にスイッチが付いたもの、USBポート付きの電源タップなど、100円以上の価格帯(200円~500円商品)も含めて多種多様な製品が並んでいます。
私の印象では、ダイソーは高価格帯の商品になるほど、作りがしっかりとしており、家電量販店の廉価品に引けを取らない品質のものも見受けられます。
もしダイソーで選ぶのであれば、少し予算を足してでも、スイッチ付きや作りのしっかりした高価格帯の電源タップを選ぶのが賢明な選択と言えるでしょう。
次の章からは、セリアとキャンドゥの製品について、さらに詳しく見ていくことにします。
この鉄則5か条を武器に、安全で便利な100均ライフを送りましょう。
【店舗別】安全な100均延長コードの選び方
ダイソー
セリア
キャンドゥ
延長コード
電源タップ
この100均延長コードなら大丈夫!ダイソー、セリア、キャンドゥの店舗別に安全な電源タップの選び方を徹底ガイド。各社で販売されている製品の種類や特徴、安全性の違いを比較します。火事を防ぐために必ず確認したいPSEマークや許容ワット数など、具体的なチェックポイントを解説。もう製品選びで迷いません。
- セリアで買える延長コード・電源タップの特徴と安全性
- キャンドゥで買える延長コード・電源タップは使える?
- 100均の延長コードは大丈夫?まとめ
セリアで買える延長コード・電源タップの特徴と安全性
さて、次はデザイン性の高い商品で人気のセリアを見ていきましょう。
「おしゃれなインテリアに馴染む延長コードが欲しい」と考えた時に、まずセリアを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
白や黒、グレーといったモノトーンカラーや、木目調のデザインなど、生活感を感じさせない製品が揃っているのがセリアの大きな特徴です。
私も先日、市場調査のために近所のセリアに足を運んでみました。
2024年の春のことです。
電気用品のコーナーに並んでいたのは、やはりシンプルなデザインの製品が中心でした。
特に主力となっているのは、長さ1mから2m程度の、差込口が一つだけのシンプルな延長コードです。
ここで、先ほどの「安全な選び方鉄則5か条」に沿って、商品をじっくりと観察してみました。
まず、手に取ったいくつかの製品は、すべてパッケージの裏面に丸形のPSEマークと「合計1500Wまで」という表記がはっきりと記載されており、第一関門はクリアです。
この点は非常に好感が持てますね。
次にプラグ部分を確認すると、ほとんどの製品にトラッキング火災を防止するための絶縁カバーが標準で装備されていました。
100円という価格で、この安全への配慮がされているのは素晴らしいことです。
しかし、専門家として少し気になった点も正直にお伝えしておきます。
それは、コードの質感と本体のプラスチック樹脂の品質です。
デザイン性を重視しているためか、一部の製品ではコードがやや細く、しなやかさに欠ける印象を受けました。
また、コンセント本体のプラスチックも、ダイソーの高価格帯商品などと比較すると、少し肉薄でチープに感じられるものがありました。
もちろん、これらはすべてPSEの基準をクリアしている範囲内での話であり、すぐに危険だというわけではありません。
ただ、長期間にわたる耐久性や、万が一の異常発熱時の溶けにくさといった点では、価格なりの差が出てくる可能性がある、ということです。
では、セリアの延長コードはどのように付き合っていくのが賢いのでしょうか。
私の見解としては、「用途を限定した軽負荷での使用」が最適解だと考えます。
例えば、スマートフォンの充電器や、LEDのデスクライト、消費電力の少ないオーディオ機器など、大きな電力を必要としない家電に使うのであれば、何の問題もないでしょう。
デザインも良いので、見える場所で使うのにも適しています。
しかし、その一方で、キッチンで使う電子レンジや電気ケトル、冬場に使う電気ストーブやこたつ、リビングで使うドライヤーといった、いわゆる「熱を発する家電」にセリアの延長コードを接続するのは、正直なところお勧めできません。
これらの高出力な家電には、やはりもっと余裕のある設計の、しっかりとした電源タップを使うべきです。
セリアの製品は、あくまで「デザインと価格を両立させた、軽作業用のパートナー」と位置づける。
この割り切りこそが、安全でおしゃれな暮らしを実現する秘訣なのです。
キャンドゥで買える延長コード・電源タップは使える?
最後に、個性的な品揃えでファンも多いキャンドゥの延長コードについて見ていきましょう。
キャンドゥは、時に「こんなものまで100円で?」と驚かされるような、ユニークな便利グッズが見つかるのが魅力です。
その波は、電気用品にも及んでいるのでしょうか。
私がキャンドゥの店舗を訪れて感じたのは、延長コードや電源タップの品揃えは、ダイソーやセリアと比較すると、やや少ない傾向にあるということです。
店舗の規模にもよるでしょうが、基本的な1mや2mの延長コードが数種類置かれている、という印象でした。
しかし、少数精鋭とでも言うべきか、キラリと光る工夫が施された製品に出会えることもあります。
例えば、以前私が見つけたキャンドゥの製品には、コンセントの差し込み口に「ホコリ防止シャッター」が付いていました。
これは、使っていない差込口にホコリが入るのを防ぎ、トラッキング火災のリスクをさらに低減させるためのものです。
家電量販店で売られている数千円クラスの電源タップには標準装備されていることが多い機能ですが、これを100円の製品に搭載してきたのには、正直感心させられました。
こうした「かゆい所に手が届く」ような製品を見つけられるのが、キャンドゥを巡る楽しさかもしれません。
もちろん、キャンドゥの製品を選ぶ際にも、これまでに何度もお伝えしてきた「安全な選び方鉄則5か条」が絶対的な基準となります。
PSEマーク、1500Wの表記、絶縁カバー付きプラグといった基本をクリアしていることは大前提です。
その上で、ホコリ防止シャッターのような付加価値がある製品を選べば、より安全性を高めることができるでしょう。
ただし、セリアの製品と同様に、やはり耐久性やコードの品質については価格相応であると考えるべきです。
私が手に取った製品の中には、コードが少し硬めで、頻繁に抜き差ししたり、曲げ伸ばしを繰り返したりするような使い方にはあまり向かないかな、と感じるものもありました。
長期間、同じ場所で曲げたまま固定して使うと、コード内部で銅線にストレスがかかり、断線に繋がる可能性も否定できません。
結論として、キャンドゥの延長コードは「使えるか、使えないか」で言えば、間違いなく「使えます」。
ただし、それにはセリアと同様、「消費電力の少ない機器に、負荷のかからない使い方で」という条件が付きます。
時計やラジオ、扇風機といった機器であれば大丈夫でしょう。
重要なのは、どの100均ショップで買うか、という「店の看板」で判断するのをやめることです。
ダイソーだから大丈夫、キャンドゥだから不安、ということでは全くありません。
一つ一つの「製品」を自分の目で見て、触って、表示を読んで、その品質を確かめる。
そして、その製品の性能に見合った「使い方」をする。
この原則さえ守れば、キャンドゥで見つけた掘り出し物の電源タップも、あなたの生活を安全に、そして便利にしてくれるはずです。
100均の延長コードは大丈夫?まとめ
長い時間、お付き合いいただきありがとうございました。
30年以上この仕事に携わってきた専門家として、そして一人の消費者として、100均の延長コードという身近なテーマについて、私の知るすべてをお話ししてきました。
さて、最後の問いに戻りましょう。
「100均の延長コードは、本当に大丈夫なのか?」
その答えは、もはやあなたの心の中にあるはずです。
そうです、答えは「あなた次第」なのです。
製品に書かれた「合計1500Wまで」という約束を守り、ドライヤーや電子レンジのような食いしん坊な家電には決して使わず、タコ足配線やコードを束ねるといった危険な行為をしない。
この、ごく当たり前のルールを守れるのであれば、100均の延長コードはあなたの良き相棒となってくれるでしょう。
しかし、「面倒だから」「ちょっとくらい平気だろう」という油断が少しでもあるのなら、そのコードはいつか牙をむく危険な存在に変わり果ててしまいます。
私からの最後の提案です。
100均の延長コードは、その手軽さと価格から、あくまで「一時的な利用」や「スマートフォン充電などの軽負荷な用途」に限定して活用してください。
そして、パソコンやテレビ周り、キッチンといった、日常的に多くの電力を使い、長期間差しっぱなしにする場所には、ぜひ、もう数百円、千円を投資して、家電量販店で安全機能の付いたしっかりとした電源タップを選んでほしいのです。
過電流が流れた時に自動で電気を遮断してくれる「安全ブレーカー」や、落雷から機器を守る「雷サージ保護」、そして「ホコリ防止シャッター」などが付いた製品は、あなたの目に見えないところで、常に家族と財産を火事のリスクから守ってくれます。
たった数百円の違いで手に入る、その「安心」は、何物にも代えがたい価値があると思いませんか。
あなたのその賢明な選択が、未来の安全を作り上げるための、最も確実で、最も重要な第一歩になるのです。
どうか、電気と正しく、そして安全に付き合っていってください。
それが、私の心からの願いです。
参考